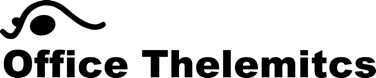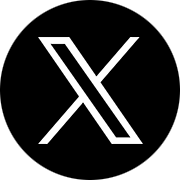| 自由研究室 |
なぜ茶室の戸は閉められなければならなかったのか
第3章 千利休とは
待庵に見る利休の茶の湯空間
利休作と伝えられる唯一の茶室
茶の湯を大成させたと言われる利休が、どのような茶室を手掛けたのか。
最も興味深いことですが、利休が手掛けたという来歴が明らかな茶室は現存していません。唯一、江戸時代から利休作または利休好みと語られてきた茶室が、京都山崎のお寺「妙喜庵(みょうきあん)」にある待庵(たいあん)です。
天正10年(1582年)の「山崎の戦い」で、陣中の苦労を一服の茶によって癒すため、秀吉が利休に命じて造らせた、とも伝えられていますが、山崎城または山崎にあった利休屋敷に建てられた後に一度解体され、その後、妙喜庵に移築されたと考えられています。侘び茶の空間美の完成型として、以後の茶室の流れを変えた言われています。
茶室の広さは、利休の師である武野紹鷗以来、四畳半が規範とされてきましたが、待庵の茶室部分は二畳しかありません。後に、利休は更に空間を追い込んで一畳台目(一畳と4分の3畳)という茶室も作ったそうです。もはやゲストを招くというよりは、ひとり座禅を組むような広さ、というより狭さです。
「躙口」の誕生

663highland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
現在でも茶室の基本要素になっている「躙口(にじりぐち)」は、待庵に初めて設けられたと言われています。枚方(ひらかた=大阪府枚方市)の漁師が、舟宿の小さな戸口を出入することからヒントを得て利休が始めたと伝えられ、壁の下部に開けられた60cm四方くらいの戸口から、茶室の座敷に潜(くぐ)るように上がるので「潜り(くぐり)」「躙上がり(にじりあがり)」などとも言います。待庵の「躙口」は、初期のものだったためか、以後の茶室よりもやや大きめのようです。
躙口について少し説明を加えておくと、小さく狭くしたのには、ある意図もあったようです。戦国の世であったとはいえ、ここを通り抜けるには、どんな身分の人でも身をかがめて頭を下げ膝をついて潜らないといけませんでした。刀は持って入れず、刀掛けが外にある茶室もあります。俗世間のものは持ち込めない、板戸を閉じ掛金までして、茶室を特別な空間としたようです。
師匠の紹鷗が北向きの茶室を好んだのに対し、弟子の利休は南向きだったそうです。弱い光の方が道具の見え方が良い、というのが北向きの理由でした。「向き」というのは出入り口のことを指していますが、利休は、障子を2枚立てて立ったまま出入りできる貴人口(きにんぐち)を廃して壁で閉じ、光を通さない板戸の「躙口」を出入り口とすることで、空間の閉鎖性を高めました。その代りに窓を適切に配することで、室内の明るさや光の当たる場所を適切にコントロールしようとしたようです。待庵においても、下地窓(したじまど)や蓮子窓(れんこまど)と呼ばれる、大きさや趣の異なる窓を巧みに配置しています。
「露地」の役割
茶室には「露地(ろじ)」と呼ばれる庭があります。この庭は、茶室とともに茶の湯空間の一部であって、眺めるための「庭」ではなく茶室に通ずる道なのだそうです。つまり露地に入った瞬間から茶の湯は始まっているのです。露地のことを、利休は「浮世の外ノ道」「妄念を捨てて、仏心を露出するによって、このように名付ける」などと説いたようです。
利休の露地は、極端に山深い印象があったと伝えられています。落ち葉が散っても掃除をしない、山奥の寺へ導かれるような風情を、そのまま残していたようです。「市中の山居(しちゅうのさんきょ)」人里にあって山里にいるかのような、日常から非日常へと誘(いざな)う通路として、世俗を断ち、自我を捨てて仏心を露(あら)わにする場として、露地はその役割を担っていたと言えそうです。